 アッパー
アッパーセンスないねって言われたこと、ありますか?
私はあります… …
当ブログ管理人のアッパーです。
この記事では千葉雅也さんの著書「センスの哲学」を紹介します。
- 読んでみたいけど、先に内容を確認したい人向けの要約と
- すでに読み終えた人向けに、オススメの関連書籍も紹介します
- センスを上げる日々の行動もリストアップ
下の目次から読みたいところだけ選んでも大丈夫です。
そもそも「センス」ってなに?
「センス」という言葉は、漠然と「おしゃれ」「才能」「勘の良さ」といった意味で使われがちです。
しかし、千葉雅也氏の『センスの哲学』は、こうした曖昧な印象を超えて、センスを「思考の技術」として捉え直します。
本書では、感性と論理のバランス、日常生活に潜む違和感の重要性、そして自分なりの判断軸を持つことの大切さが語られています。
単なる「感覚」ではなく、磨き、鍛え、構築するものとしてのセンス。
この本を読むことで、あなたの感覚は「なんとなく」から「意識的」へと進化します。
センスの哲学とは何か ― 感性と論理の橋渡し
『センスの哲学』の核心は、感性と論理を対立させるのではなく、相互補完的に働かせるという発想です。



センス=感性だと思ってました… …
感性は瞬時の判断や直感を生み出しますが、それだけでは独善的になりかねません。
一方、論理は正確で筋道立った思考を可能にしますが、感情や人間らしさを欠くことがあります。
千葉雅也氏は、この両者を行き来しながら意思決定を行うことが「センスの本質」であると説きます。
センスを磨くための「違和感」の活用法
本書で特に印象的なのは、「違和感」を感性のトレーニング素材として活用するという考えです。
私たちは普段、馴染みのあるものに安心感を覚え、違和感を避けがちです。



いつものお店で、いつものメニューを頼みがちですよね
しかし、その違和感こそが新しい視点を開き、感性を成長させるきっかけになります。
千葉氏は、日常の中で感じる小さなひっかかりを無視せず、言語化し、他者と共有することが重要だと述べています。
日常生活に潜む「哲学的思考」の入口
『センスの哲学』は難解な哲学書ではありません。
むしろ、コンビニでの選択や、SNSの投稿、友人との会話といった日常の場面から哲学的な問いを引き出す実践的な指南書です。
哲学は特別な場でだけ行うものではなく、生活の中で繰り返し行える小さな思考の習慣。
この「日常哲学」の実践こそ、センスを継続的に磨く土台になります。
「センスがない」を変える方法
多くの人は「自分にはセンスがない」と思い込みます。
しかし千葉氏は、センスは生まれつきの才能ではなく、環境と経験によって形成されると指摘します。
具体的には、
- 良質なインプットを増やす
- 自分の感覚を言語化する練習をする
- 他者からのフィードバックを受ける



私は読書でインプットを増やしています!
この3つが、センス向上のための基本サイクルです。
センスを「人生観」に組み込むために
本書の魅力は、センスを単なる表面的なスキルではなく、自分の生き方や価値観と結びつける視点にあります。
服装やインテリアのセンスも、会話や仕事のセンスも、根底には「何を大事にするか」という人生観が反映されます。



好きなものに熱中することが、センスを磨くことになります
千葉氏の哲学は、センスを生き方の軸に据えることで、日常に深みと方向性をもたらすヒントを与えてくれます。
【まとめ】忙しい人はここだけ読んでください!
『センスの哲学』は、感性と論理の行き来を通して、自分らしい判断軸を作るための本です。
違和感を避けず、日常の中で哲学的思考を積み重ねることで、あなたのセンスは確実に磨かれます。
本書を読むことで、単なる「なんとなくの感覚」が「根拠のある感性」に変わり、日々の選択や行動がより自信を持って行えるようになるでしょう。
【実践アクション】
- 毎日ひとつ違和感をメモする
- SNS投稿に自分なりの理由を添える
- 興味のないジャンルの本を読む
- 他人の選択基準を聞く
- 日常の判断理由を言語化する
- 会話で相手の言葉を引用して返す
- 写真を撮り感性の記録を残す
- デザインや色使いを観察する習慣を持つ
- 行ったことのない店に入る
- 意見が違う人とあえて話す



上記のリストに気になるものがあれば、「センスの哲学」はあなた向きの本だと思います。
既に読み終えた人は、併せてコチラもどうぞ!
同じく千葉雅也氏の著作「勉強の哲学」
「センスの哲学」でセンスを磨く術を学んだあとは、「勉強の哲学」で「空気」に支配されず、自分らしさを伸ばす方法を知るのがオススメです!
下の記事で要約が読めます。よければどうぞ
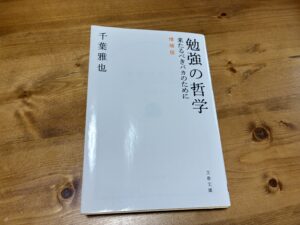
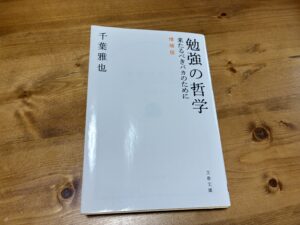
要約を読む時間がない!
そんな方は、目次だけでも目を通してみてください。
せっかく磨いたセンス。個性も加えてさらに伸ばしていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
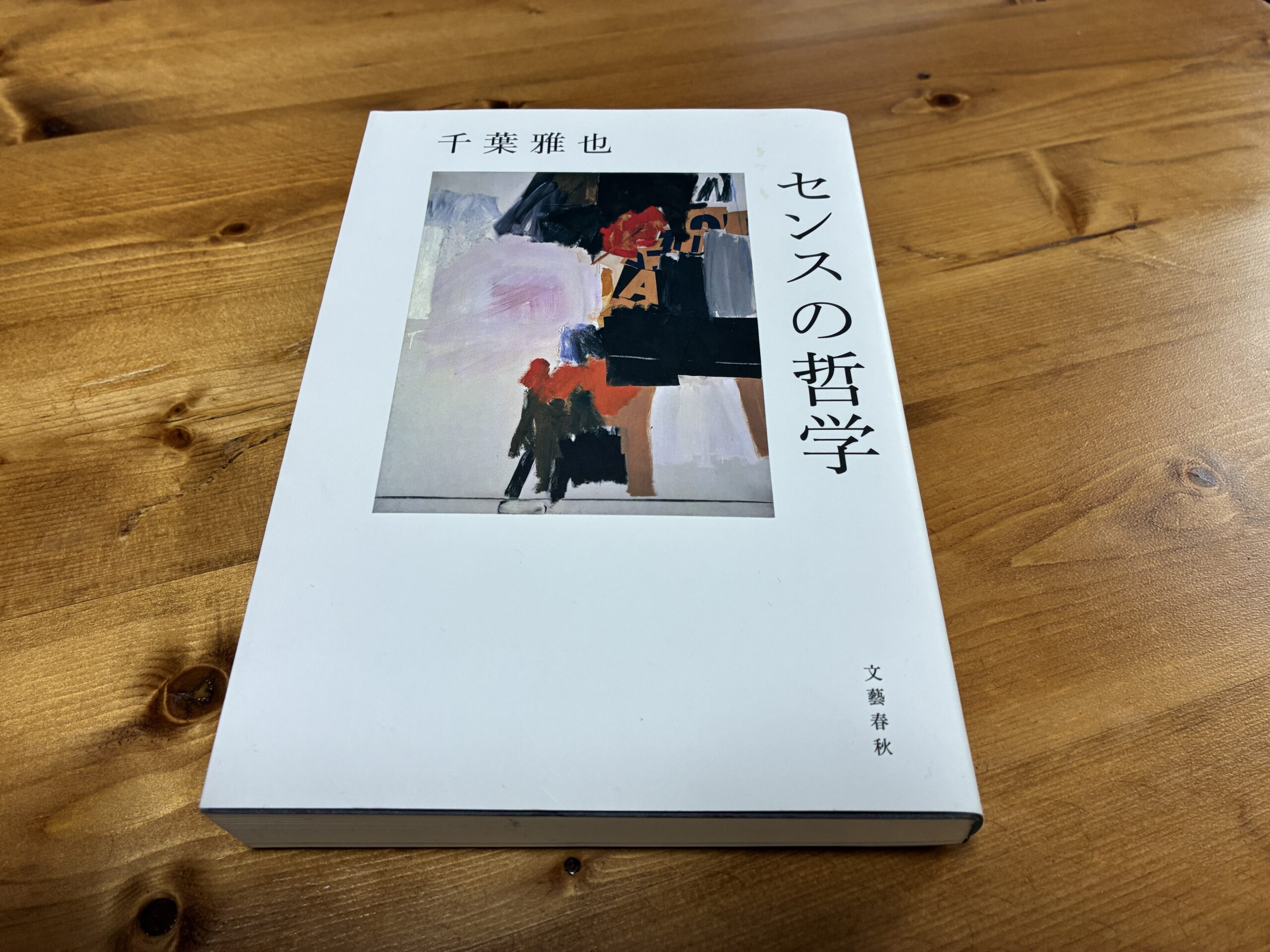
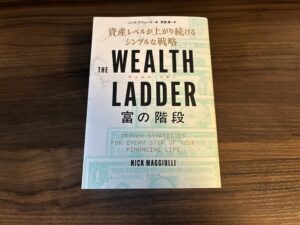

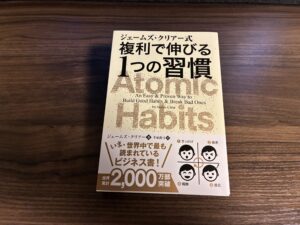
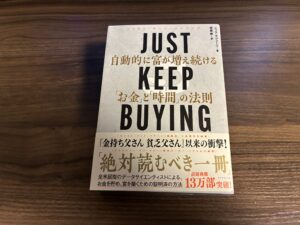
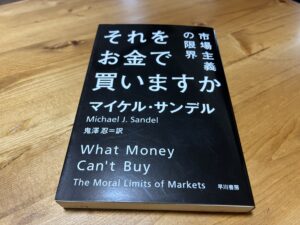
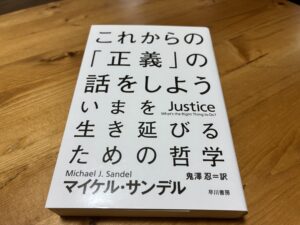
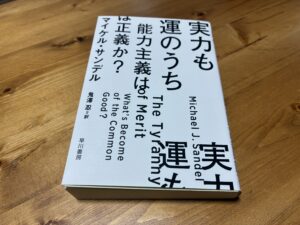
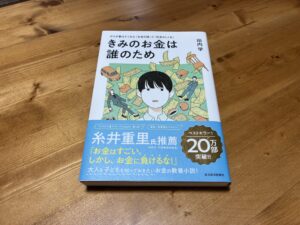
コメント