 アッパー
アッパーこんにちは! 当ブログ管理人のアッパーです!
この記事では、養老孟司さんのロングセラー「バカの壁」を要約します
- すでに読み終えた人向けに関連書籍も紹介しています。
下の目次から気になるところへ飛んでもOK!
どんな本なのか?



この人、なんでわかってくれないの?
そんなイライラを感じたこと、ありませんか?
自分の言いたいことは正しいのに、なぜか伝わらない。
職場や家庭、SNSでのやりとりで、誰もが一度は経験している“分かり合えなさ”。
養老孟司さんのベストセラー『バカの壁』は、まさにその「わからなさ」の正体に切り込む本です。
「壁があるのは相手がバカだから」ではなく、「壁に気づかない自分にも原因がある」――。
そんな痛烈な気づきを与えてくれるこの本は、読後の人間関係を大きく変える一冊になるかもしれません。
個性を貫いても伝わらないもどかしさ
「自分はこう思う」と主張しても、なぜか空気が凍る。そんな経験、ありませんか?
私は「個性を大事に」と育てられたけれど、社会では「空気を読まないと」生きていけない。



思いっきり矛盾してますよね
『バカの壁』を読んで初めて、そんな矛盾が腑に落ちました。
他者と共有している前提が違えば、いくら言葉を尽くしてもすれ違うだけ。
共通了解の存在を前提にしなければ、個性もただの独りよがりになる。
その視点は、私の中で本当に大きな転機でした。
自分の「正しさ」が壁を作っていた



「論理的に話せば伝わるはず」と思っていました
でも、それは自分の世界を“正解”と信じていた証拠。
『バカの壁』は、その「正しさ」こそが壁を作っていると教えてくれます。
他人の話を聞くときも、無意識のうちに“自分に都合のいい情報”しか受け取っていなかった。
真に人と向き合うには、まずは自分の思い込みを疑う勇気が必要。
相手に伝わらないのは「バカ」だからじゃない



「なんでこの人、わかってくれないんだろう?」
そう思うこともたくさんありました。
でも相手も、同じように私のことを「わかってない」と思っている。
『バカの壁』は、そんな“わかり合えなさ”を前提に考える視点を与えてくれます。
コミュニケーションが成立しないとき、私たちはすぐ「相手の問題」にしがちです。
でも本当は、すれ違いの根っこには、お互いの「前提のズレ」があるんですよね。
共通了解を持たない社会で、どう生きるか
SNSを見ていると、自分と違う意見にすぐ攻撃が飛ぶ時代だと感じます。
でも『バカの壁』は、その「違い」に価値を見出すよう促してくれます。
一元的な正解が通じない現代、多様な価値観が交錯する中でどう生きるか。
“わかり合えない”ことを前提に人と接するだけで、心が少し楽になる。
共通了解が成立しづらい社会において、自分の在り方を見直すヒントが詰まった一冊でした。
『バカの壁』が教えてくれた、本当の理解とは
この本を読んで一番印象に残ったのは、「わかるとは何か?」という問いです。
私たちはすぐに「わかったつもり」になってしまう。
でも、それは本当にわかったとは限らない。
理解しようとする努力そのものが、他者への最大の敬意なのかもしれません。
『バカの壁』は、“わかろうとし続けること”の大切さを、静かに語ってくれる本でした。
まとめ!
人間関係に悩んだとき、「どうすれば相手に伝わるか」と考えがちです。
でも『バカの壁』は、そもそも“伝わらないこと”が前提だと教えてくれます。
その前提に立つと、他人とわかり合えなくても焦らなくなります。
自分も、相手も、思っているほど「正しくない」ことに気づくだけで、世界が少し柔らかくなるのです。
自分の正しさに疑問を持ったときこそ、『バカの壁』を開いてみてください。
新しい「理解の扉」が、静かに、でも確実に開いていくはずです。
すでに「バカの壁」を読み終えた方は、こちらをどうぞ!
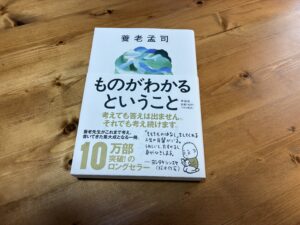
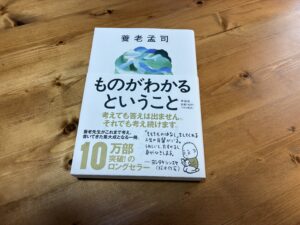
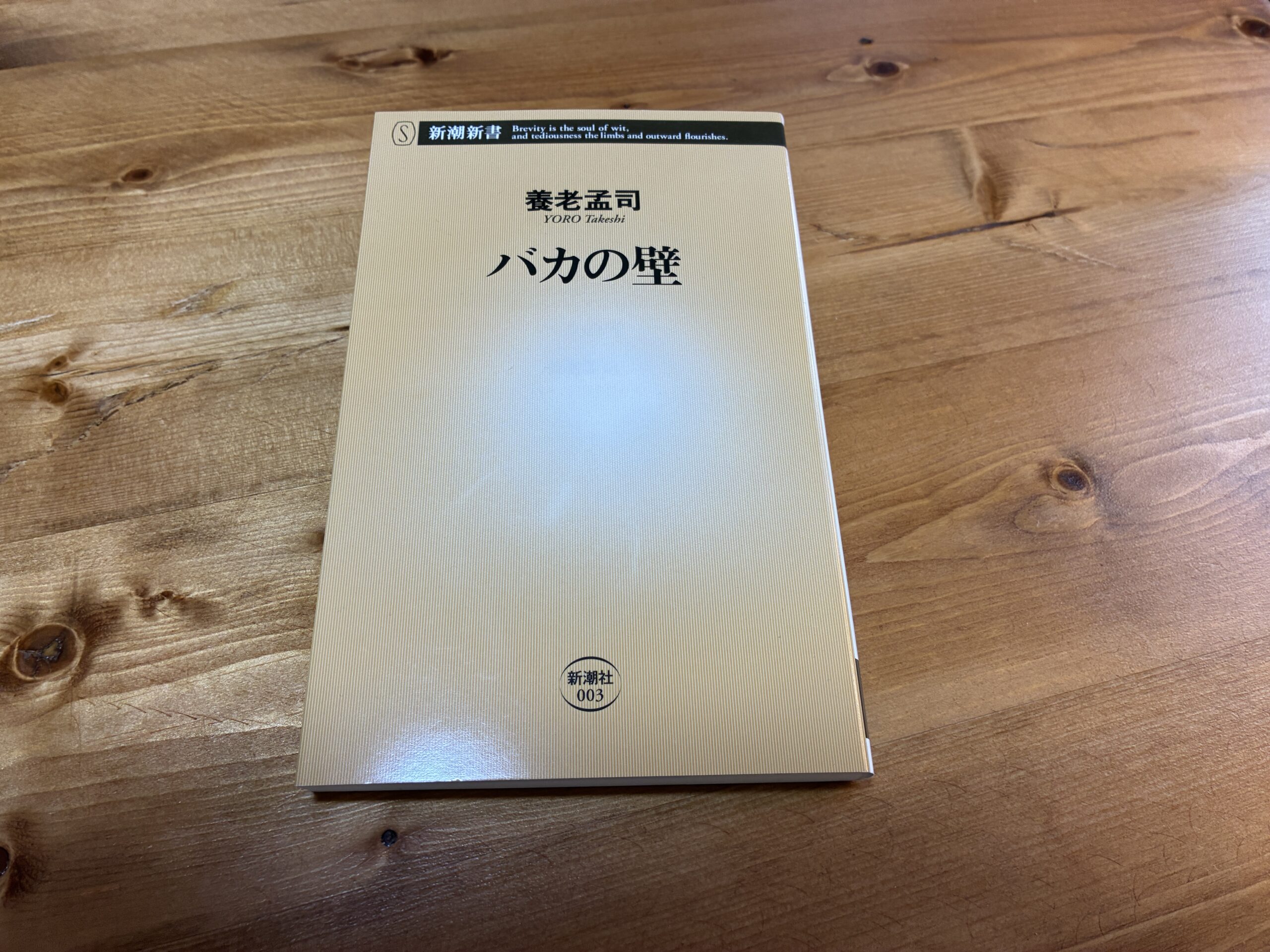
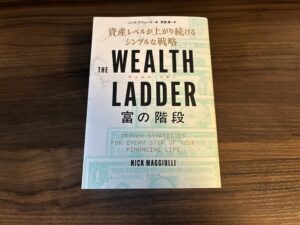

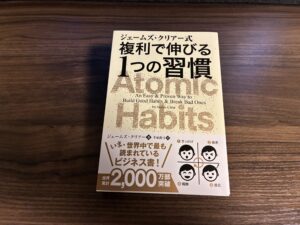
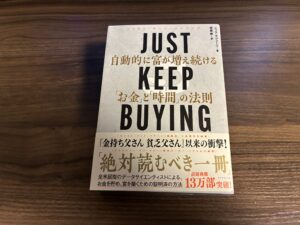
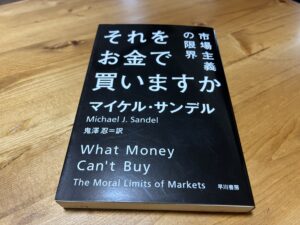
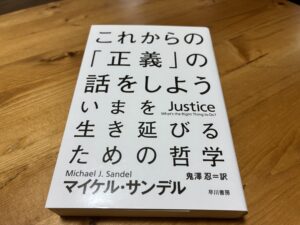
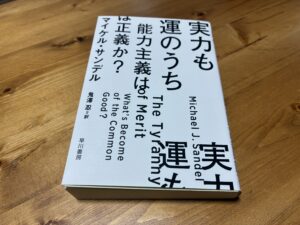
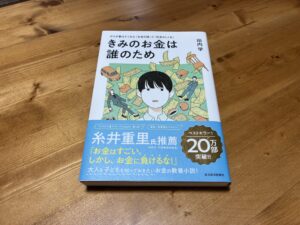
コメント