 アッパー
アッパーこんにちは! 当ブログ管理人のアッパーです
この記事では國分功一郎氏の著書「暇と退屈の倫理学」を要約しています。
- まだ読んでいない人むけの要約はもちろん
- すでに読んだ人にオススメな関連書籍も紹介します
結論&実践アイディア
- 暇と退屈は別物
- 現代人は忙しく、暇はないのに退屈している
- 定住し、能力を持て余すようになった
- 終わりのない消費サイクルに囚われた人生
上記のような状態を避けるために、私たちに何ができるのか。
- まずは「暇と退屈の倫理学」を読む。
- 終わらない消費を避け贅沢な浪費を楽しむ(私の場合は食事と運動)
- 何かしたい。欲しいと思った時は「欲望の目的と原因」を考えてみる
- 日常に変化をつける(いつもと違う道で帰るとか、普段食べないものを食べるとか)
なぜ、貴方は退屈しているのか?
なんか退屈だな。
誰もが一度はしたことのある呟き。退屈を感じることに、私たちに何が起きているのか?
本書の中では退屈の反対は快楽ではなく「興奮」であると解説されています。
興奮を呼び起こすトリガーとして「事件」が必要。
昨日と今日を区別するような「非日常」の体験。それが事件であり、日常が続くと私たちは退屈してしまうそうです。



平日の学校や仕事。退屈だなって思う時ありますよね
私たちが退屈するのはなぜか。理由は単純で、日常に変化がないからです。
「暇」と「退屈」の違いを知っていますか?
暇と退屈。誰でも口にしたこのある言葉だけれど、意識的に使い分けている人はいないと思います。
著者はこの二つを明確に区別し、その組み合わせとして4つのパターンを提示しています
- 暇はなく退屈もない
- 暇であり、退屈である
- 暇はあるけれど、退屈している。
- 暇はないのに、退屈している
1と2はわかりやすいですね。忙しい時と、ボケっとしている時です。
3番の暇はあるけれど退屈している状態。これは貴族の生活で、生きるためにすることは使用人がやっている(暇がある)。そして生活は安定している(変化がなく退屈)
そして現代人の多くは4番の「暇はないのに、退屈している」状態に陥っているようです。
貴族ほどの余裕はなく(暇はない)けれど日常に大きな変化はなかなか起きない(退屈している)
貴方の生活。仕事や学校はどれに当てはまりますか?
暇はないけれど退屈という矛盾
こんな矛盾に私たちが陥っているのはなぜか。
消費社会では時代の移り変わりが早く、新しいものがすぐに古くなってしまう。そうすると人々は、今の生活に満足できず退屈し始め、その退屈を紛らわせるために新しいものを(変化を)求める。
その欲求が流行り廃りのペースを加速させ、私たちはさらなる退屈へと陥ってしまう。



スマホのニューモデルが出るペースめちゃくちゃ早いですよね… …
そんな状態からどう抜け出せばいいのか?
それは、贅沢をすること!
浪費と消費の違い。贅沢をすると豊かになれる理由
贅沢をしたら豊かになれるって言われても
普通に考えれば、贅沢な暮らしをすればお金がなくなり、貧しい思いをすることになります。
でも「暇と退屈の倫理学」では違います。
それは「浪費」と「消費」を分けているから。
消費に限界はないが、浪費には限界がある。
どういうことでしょうか?
この本における消費とは、ものを受け取る代わりに、情報を受け取るものだと思ってください。
例えば、新しくオープンしたお店に行きたいと思った場合です。
その人は料理を食べたい(ものを受け取る)のではなく、新しくオープンしたお店に行ったという経験(情報を受け取る)を求めているのです。



料理ではなく、お店に行ったという事実が欲しいといこと!
そのような行動を、この本では「観念的行動」と紹介しています。
それに対して、ものを受け取る活動が浪費。
例えば食事。食事には胃袋の大きさという限界があります。1日に食べられる量も、一生の間にできる食事の回数も限られている。
だからこそ、贅沢が許される。贅沢をしたとしても、無限に続くことはない。
そして人は満足を覚えるのです。美味しいものを食べた時の、ただ満腹になったのとは違う充足感。
その感覚が「浪費」です。
浪費と消費の違いを知った上で、私たちはどんな行動を取ればいのか?
日常の中から、「終わりのない消費」と「贅沢な浪費」を見極めること。
退屈だと感じた時、情報ではなくモノに目を向ける。
それでも退屈に陥らずに生きるのは難しいのです。
なぜなら退屈には種類があるから。
すでに「暇と退屈の倫理学」をp読み終えた方へオススメ!
- 「それをお金で買いますか」
- 「お金の減らし方」
退屈には種類がある



退屈は3種類! そして二つ目が厄介です
退屈の第二形式は「何かに際して退屈すること」。
それは退屈を紛らわせるはずの「気晴らし自体が退屈を催す」ような状態です。
やることがなくて、なんとなく手に取ったスマホ。SNSを眺めてもこれと言って面白いものはなくて、ただなんとなくスクロールし続ける。みたいな状態。退屈のための気晴らしが退屈をもたらす。
厄介な矛盾ですね。
そしてこの矛盾は上記の「暇はないのに退屈」という矛盾と繋がっています。
さらに厄介で深刻な三つ目の退屈もあります。
それは「なんとなく退屈だ」という状態。
それだけ?
そう、これだけ。特に理由も思いつかず、解決策もなく、ただなんとなく退屈。退屈だな、という声がふと脳裏をよぎる瞬間が最も深刻な三つ目の退屈です。
それに対して、私たちはどうすればいいのか?
退屈している=何もやる気にならない
だから、とにかく決断してしまおう。というのが一応の解決策です。
ただ、これには罠があります。



実は一つ目と三つ目の退屈は同じもの
詳しい解説、根拠は本書をお読みいただくとして、この記事では一足とびで話を進めていきます。(何せ要約ですし)
退屈に際し、決断をすることは罠かもしれない。
なぜなのか?
それは、決断は気持ちがいから。そして選んだことへ盲目的に従ってしまうから。
他に大切なことがあるかもしれないのに、ただひたすら仕事に打ち込んだり、生きがいだからと自分に言い聞かせて自己実現に邁進したり。
その選択が正解ならいいのですが、人は間違える生き物なので、盲目的になるのは危ないと思います。
では、どうすればいいのか? 退屈に際し、行動を起こすことがリスキーなら、退屈に耐えるしかないのでしょうか?
すでに「暇と退屈の倫理学」を読み終えた方へオススメ!
- 「存在と時間」
- 「史上最強の哲学入門」
- 「生物から見た世界」
人間的自由の本質と環世界移動能力
この世界には多様な生き物が生息しています。
そんな常識に対して本書ではユクスキュルの「環世界」という理論を提示しています。
- 生物は独自の世界を持っており、時間や空間は共通ではない。
- そして一部の生物は今いる環世界から違う環世界へと移動することができる
- 人間はその環世界移動能力が極めて高い
「暇と退屈の倫理学」で重要になるのは上記の三点です。
この環世界を移動するために必要なものが、習慣の形成。



新しいことを始めると、今まで気づかなかったことに気づけるようになりますよね!
習慣の形成による環世界の移動。これがいわゆる非日常体験で、退屈とは真逆の状態です。
でも、どんな非日常も続けるうちに日常となり、習慣になってしまう。
そして私たちは退屈し始める。
習慣が出来上がると退屈し、退屈を紛らわすために新しいことを始めても、やがて慣れて退屈が訪れる。
このループは一見すると不満を覚えるかもしれません。けれど、よく考えるとそんなに悪いものでもない。
退屈と気晴らしのループは私たちに挑戦や学習を促してくれるからです。
定期的な退屈を伴う代わりに、違う環世界へと移動し続けることが、人間的な自由なのかもしれませんね。
すでに「暇と退屈の倫理学」を読み終えた方へオススメ!
- 「群集心理」
- 「自由からの逃走」
- 「服従の心理」
まとめ!
本書では結論が三つ用意されています。
- 「暇と退屈」について、こうしなければ、と思い煩う必要はない
- 「贅沢を取り戻すこと」
- 「動物になること」
この結論についてもっと詳しく知りたい人は、ぜひ「暇と退屈の倫理学」を通読してください。
当記事では「暇と退屈の倫理学」の要約をしました。
ですが要約は薄味で、通読しながら自分で咀嚼する読書には敵いません。
すでに「暇と退屈の倫理学」を読んだ方へオススメ!
國分功一郎氏の著書「中動態の世界」も常識をぶっ壊す読書体験ができるので、ぜひ読んでください!
最高な読書のために



読みたいと思った時が一番面白いし、記憶に残る!
結局モチベが高い時に読む読書が一番面白い。
本屋に行く時間がないなら、電子書籍で試し読みだけでもしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
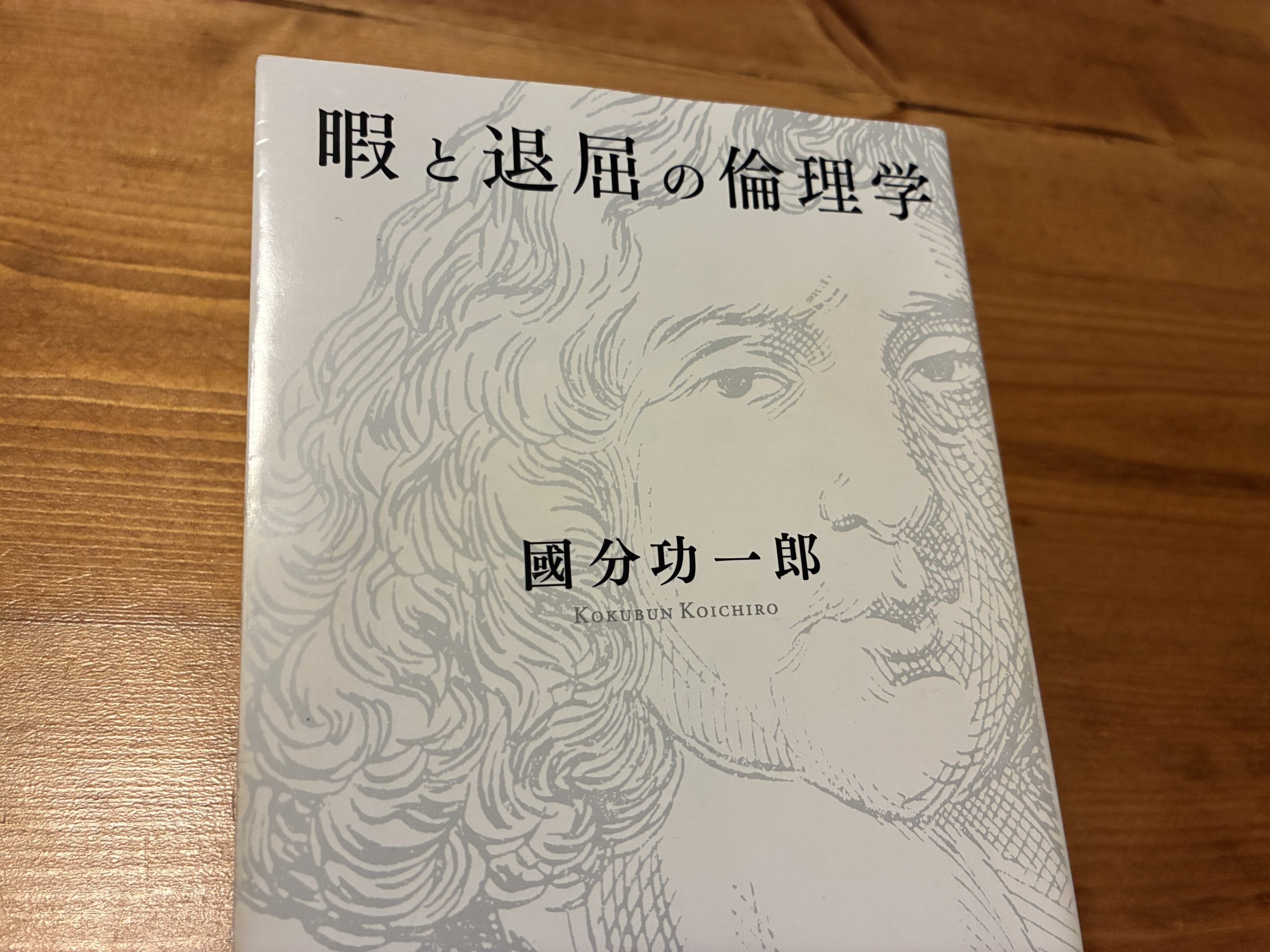
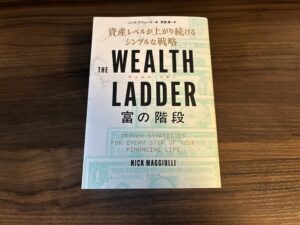

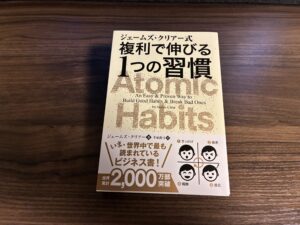
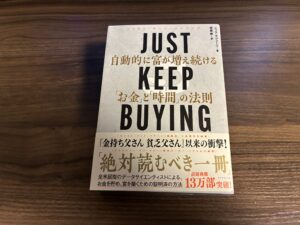
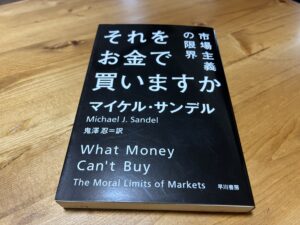
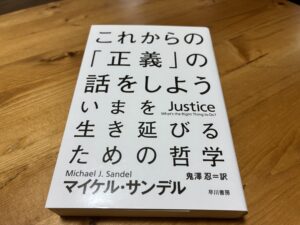
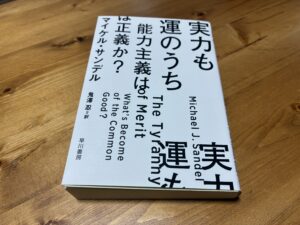
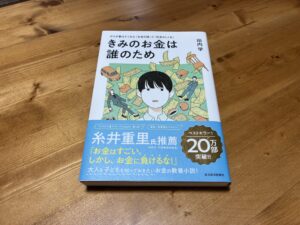
コメント