SNSの炎上、キャンセルカルチャー、過剰な監視と同調圧力。
こうした現象を「地獄」と呼んだのが橘玲の著書『世界はなぜ地獄になるのか』です。
 アッパー
アッパー正義の名の下に人々を断罪する社会で、私たちはどう生きていけばいいの?
本記事では本の要約を軸に、キャンセルカルチャーの構造とその危険性を解説し、さらに「どう生きるか」のヒントとを紹介します。
下の目次から見たいところだけ読んでも大丈夫です!
世界はなぜ地獄になるのか |ユーディストピアの罠
橘玲氏が警鐘を鳴らすのは「ユーディストピア」の罠。
ユートピアを目指すほどに、社会は逆説的に地獄のような監視社会に変貌していきます。



すでに中国は「1984年」のような世界になりつつありますよね
そんな監視社会で特に目立つものが炎上です。
小さな失敗や過去の失言が掘り起こされ、社会的制裁を受ける。
人々は「正義」を掲げながら、他人を断罪する快楽に溺れていく。
この構造を「理想郷が生む地獄」として説明するのが本書の核心です。



断罪する側に悪意がないのがポイント
橘玲が語るキャンセルカルチャーの本質
キャンセルカルチャーの根底には、「自己過信バイアス」があります。
橘玲は別の著作『バカと無知』で、人間がいかに自分の判断を過信するかを示しています。
SNS上で「自分は正しい」と信じて他人を叩く行動は、この自己過信バイアスによるもの。
つまり、キャンセルカルチャーは正義の実現ではなく、思い込みと欲望の集団化が生んだ「錯覚」だといえるのです。
結局、私たちはどうすればいいのか?
この本を読めば炎上の仕組みを理論的に捉えることができるようになります。
一方で「暗い気持ちになる」かもしれません。



結局、個人では世の中をかえられない
しかし橘玲氏は決して悲観だけを語っているわけではありません。
「現実を直視することこそ自由の第一歩だ」と強調しているのです。
その点では橘玲氏の著作『言ってはいけない』と共通しています。
不都合な真実を見て初めて、社会と個人の行動は変わり得るのです。
限りある時間の使い方との接続
ここで浮かぶ疑問は、「では私たちはどう生きればいいのか?」ということです。
そこで参考になるのが、オリバー・バークマンの『限りある時間の使い方』という本です。



私はこの本を読んで、SNSに時間を奪われることがなくなりました!
SNSの炎上やキャンセル文化に時間を奪われるのではなく、自分の有限な時間を「本当に大切なこと」に投資する視点が示されています。
地獄のような社会に飲み込まれるのではなく、限られた時間を意識して「無駄な炎上から距離をとる」ことが、精神的な自由を取り戻す方法なのです。
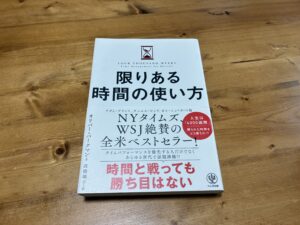
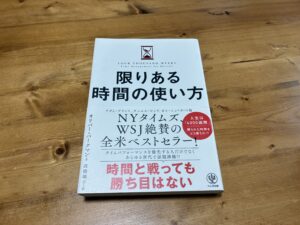
ディストピアを避けるために必要な視点
橘玲は「完璧な正義は存在しない」と強調します。
必要なのは「寛容さ」と「距離感」。
バークマンは「人は有限の存在だからこそ、やることを減らすべきだ」と説きます。
この二人の主張を組み合わせると、答えは明らかです。
「すべてを正そうとするのではなく、すべてを抱え込むのでもなく、限られた時間でできることを選び、他者には寛容であれ」ということです。
世界はなぜ地獄になるのか まとめ|時間と自由を守る生き方
『世界はなぜ地獄になるのか』は、SNS社会に対する冷静な警告書です。
そして『限りある時間の使い方』は、その中で私たちがどのように日々を過ごすべきかを教えてくれます。
炎上に加担したり、SNSへ過度にカカw流のをやめ、限られた時間を大切にする。
誰かを断罪するよりも、自分の生活を良くするための行動を選ぶ。
今日からできる行動リスト
- SNS投稿前に一度立ち止まる
- 炎上ニュースは「見ない」「拡散しない」
- 自分も裁かれる側になり得ると意識する
- 「完璧な正義はない」と心に刻む
- 他人の過去よりも現在の行動を評価する
- 『世界はなぜ地獄になるのか』を読んで地獄の構造を理解する
- 『言ってはいけない』で不都合な現実に向き合う
- 『限りある時間の使い方』を実践し、日常に優先順位をつける
- 大切な人との時間を最優先にする



できることから一つずつやっていきましょう!
すでに「世界はなぜ地獄になるのか」を読み終えた方はコチラ!



橘玲さんの代表作「言ってはいけない」は誰も教えてくれない社会の闇を暴く本です!



「限りある時間の使い方」を読めば、子供の頃のような深い集中を取り戻すことができます!



スマホの普及で世界中にカメラが溢れる現代。その更に先の未来を知りたいなら「1984年」をどうぞ!



最後までお読みいただき、ありがとうございました!
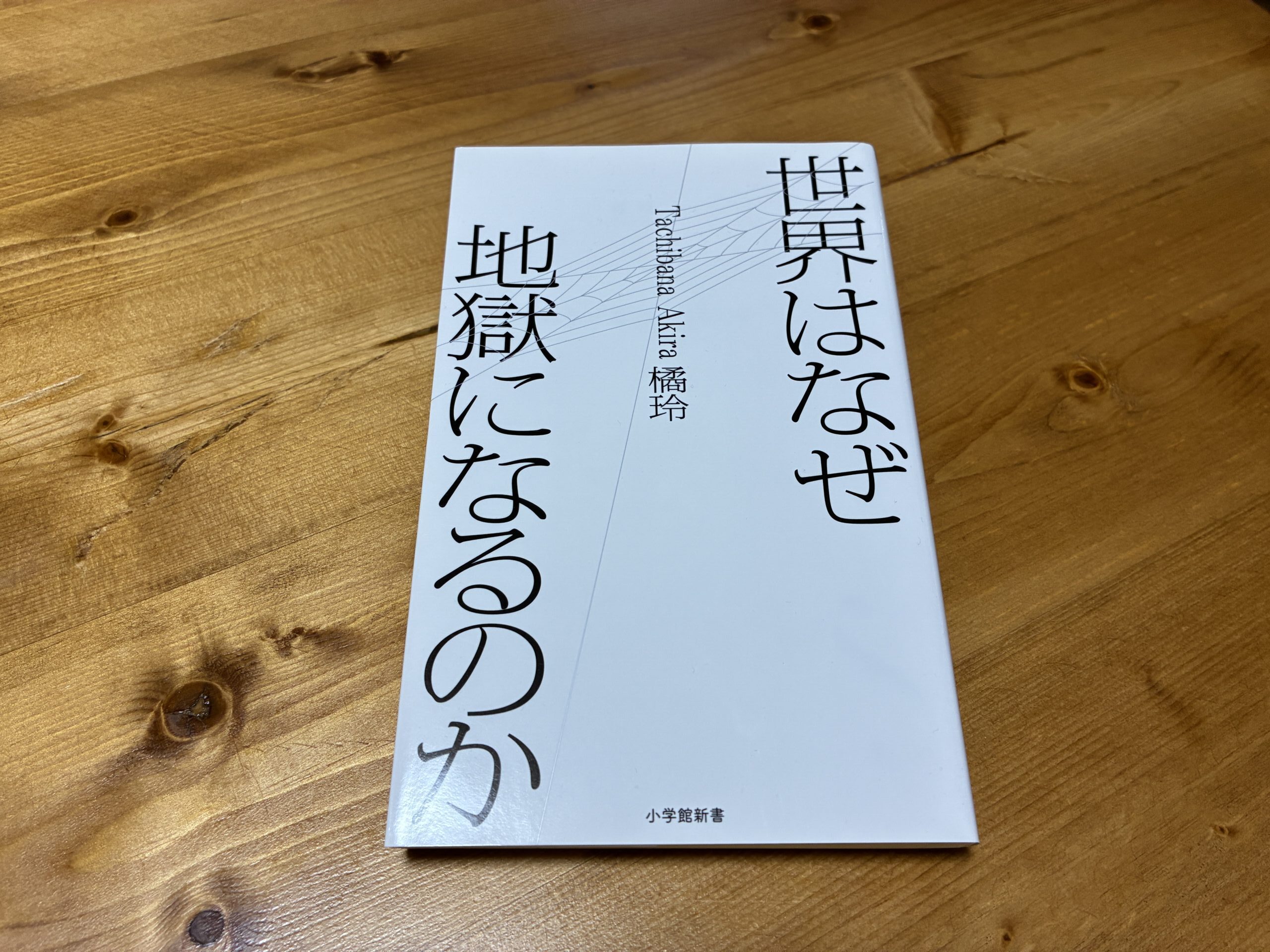
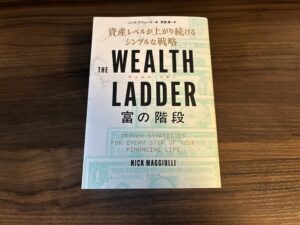

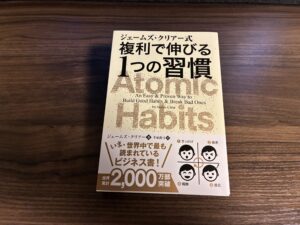
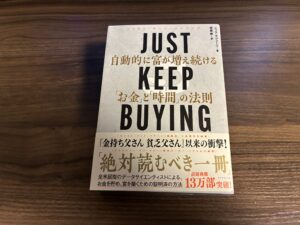
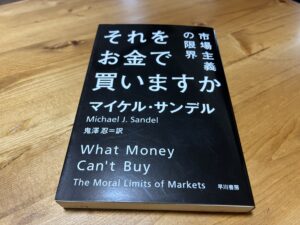
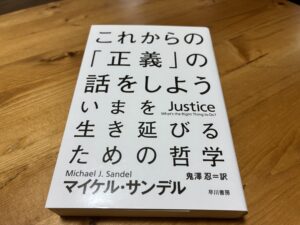
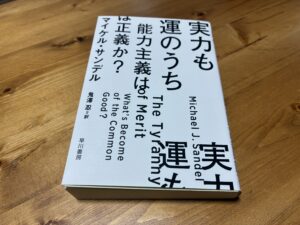
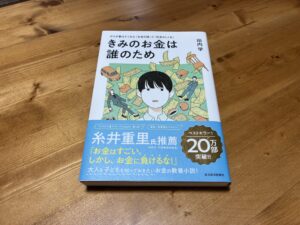
コメント