「なんでこんなにモヤモヤするんだろう?」
日常のふとした瞬間に感じる違和感。それは「わかっていない」からかもしれません。
『ものがわかるということ』(養老孟司 著)は、私たちが「わかったつもり」で生きている現実に、静かに、でも鋭く切り込む一冊です。
- 理解するってどういうこと?
- なぜ、身近な人と分かり合えないのか?
- 答えが出ない悩みとどう付き合えばいいのか
そんな疑問を抱いたことがあるなら、この本はきっと心に残る読書体験になるでしょう。
本記事では、実際に読んで感じた変化や気づきをもとに、この本の魅力を分かりやすく紹介していきます。
日常の見方が変わる『ものがわかるということ』の世界
この本を手に取ったきっかけは、日々の出来事に違和感を覚えたからでした。
 アッパー
アッパー「当たり前」って言われても
納得できないことってありますよね。
そんな人にとって、「ものがわかる」という行為そのものを問い直すこの本は、まさに転機となる一冊でした。
養老先生は、私たちが言葉やデータに頼りすぎて、本当に“感じる”ことを忘れていると語ります。
ページをめくるごとに、自分の見方がほぐれていくような感覚。
読む前には戻れない。それくらい「日常の見方」を変えてくれる一冊です。
『ものがわかるということ』要約と感想 ― 腑に落ちた学び
この本では、「わかる」という状態を分解し、言葉の裏にある無意識や身体感覚にまで光を当てています。
印象的だったのは、「わかる」はあくまで個人的な体験であり、絶対的な正しさではないという指摘。
読んでいくうちに、「わかったつもり」で人を判断していた自分に気づかされました。
知識が増えるほど、かえって視野が狭くなるという逆説。
自分の思考のクセと向き合いながら読み進めることで、理解するとはどういうことか、初めて腑に落ちた気がします。
自然と共鳴する「わかる」の本質とは何か?
養老先生が語る「自然との共鳴」には、どこか懐かしさを感じました。
都会で暮らし、情報に囲まれて生きていると、自分の感覚が何かに覆い隠されているように思うことがあります。



とはいえネットから離れることも難しい… …
でも本来、“わかる”とは、理屈ではなく「なんとなく感じる」ことから始まるのではないか。
この本は、そんな身体的な気づきを思い出させてくれました。
無理にデジタルデトックスをしなくても大丈夫。
本書を読めば、レビューやおすすめではなく、自分の感覚を通して自然を体感する方法を思い出すこともできます。
常識やデータを疑う、自由な生き方のすすめ
この本を読んでから、ニュースやSNSに触れる自分の姿勢が変わりました。
以前は「多数派の意見=常識」と無意識に思っていたけれど、それって本当に“自分で考えた”結果だったのか?
養老先生は、常識とはあくまで「その場の都合」にすぎないと語ります。
それに気づいた瞬間、なんだか肩の力が抜けたような気がしました。
データや言葉の海に流されず、自分の身体と心で「どう感じたか」を基準にする。
そんな自由さを、この本はそっと教えてくれます。
「自分がわかる」のウソと向き合う読書体験



みんなが自分のことをわかってくれない… …
理解してもらえない苦しみってありますよね。
でも実は、「私は自分のことをよくわかっている」というのが勘違いかもしれない。
周りにわかってもらえないのではなく、そもそも自分が自分を理解できていない。
この本を読んで、「自分をわかる」とはどういうことか、本当に考えさせられました。
養老先生は、人間は自分の脳の中にあることしか認識できないと語ります。
つまり、“自分”という存在もまた、見えているようで見えていない。
だからこそ、他者との対話や自然との関わりの中で、自分の枠組みが少しずつ広がっていく。
読み終えたとき、私は「わからなさ」にも価値があると気づけました。
まとめ!
読み終えて、私は自分がいかに「わかったつもり」で世界を見ていたかに気づかされました。
『ものがわかるということ』は、知識を得るための本ではなく、「考え続ける力」を育ててくれる本です。
今、もしあなたがモヤモヤした気持ちを抱えていたり、「何かを変えたい」と思っているのなら、
この本はきっと、あなたの思考に小さな風を吹き込んでくれるはずです。
すでに「ものがわかるということ」を読んだ人にオススメ!
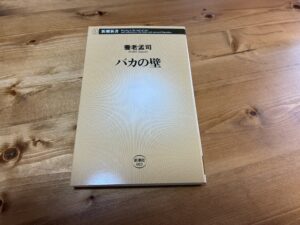
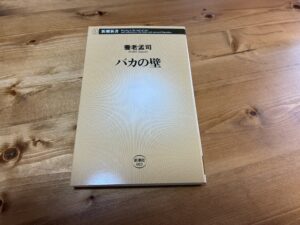
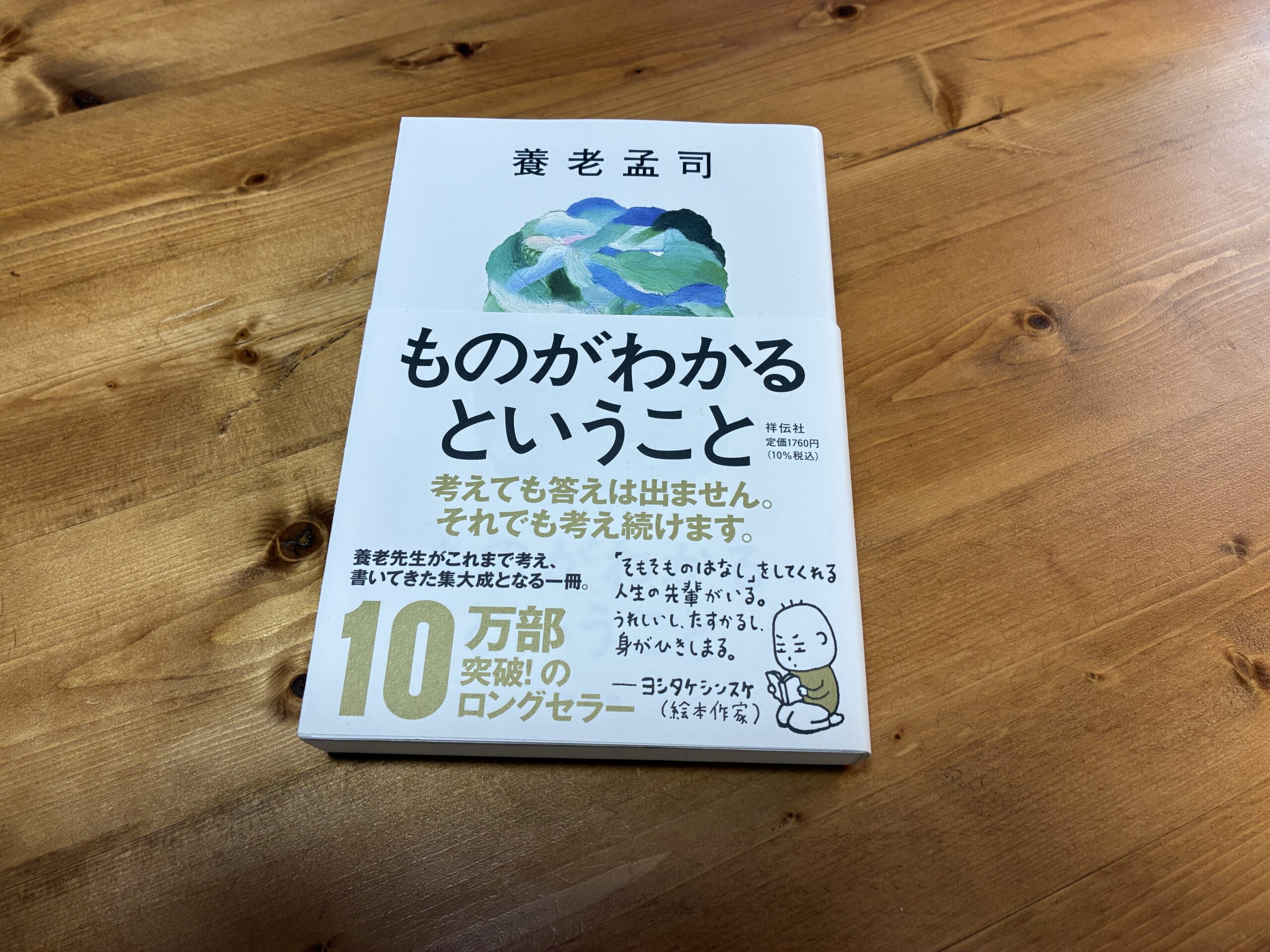
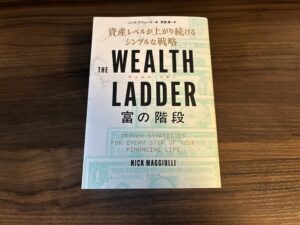

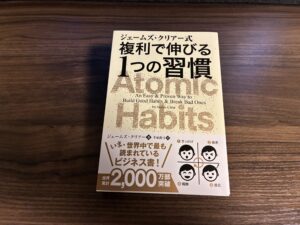
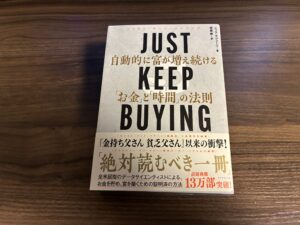
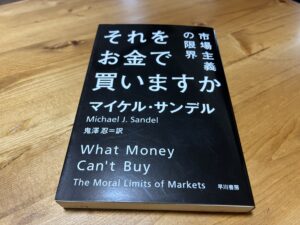
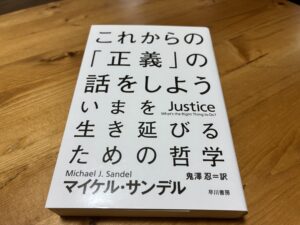
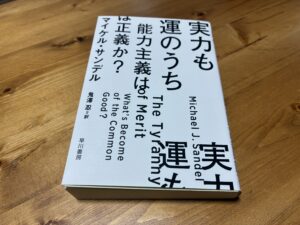
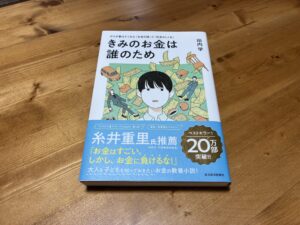
コメント